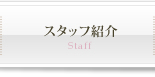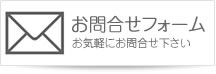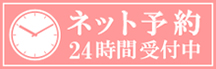スタッフブログ
最近の投稿
- 2024年7月10日 タフトブラシについて
- 2024年7月 1日 詰め物が取れた!
- 2024年6月25日 歯の色
- 2024年6月19日 40~60代のお口の中
- 2024年6月10日 親知らず
- 2024年6月 3日 虫歯より怖い歯周病
- 2024年5月31日 歯内療法セミナー
- 2024年4月23日 目で見る虫歯の進行
- 2024年3月27日 仕上げ磨きの重要性
- 2024年3月20日 唾液の働き
- 2024年3月14日 口臭と口臭チェック法
- 2024年3月 9日 生え変わらない乳歯
- 2023年12月 5日 矯正治療
- 2023年11月14日 虫歯予防のフッ素
- 2023年11月10日 インプラント周囲炎について
- 2023年11月 1日 プラークについて
- 2023年10月25日 歯の形と役割
- 2023年10月 5日 大変?歯のぐらぐら動揺
- 2023年9月29日 奥歯にかかる力
- 2023年9月26日 歯ブラシの使い方
タフトブラシについて
こんにちは。
今日はタフトブラシについてです。
皆様はタフトブラシをご存知ですか?
タフトブラシは毛束が1つのヘッドの小さな歯ブラシです。
普通の歯ブラシでは毛先が届きにくいところの清掃に適しています。
普通の歯ブラシで磨いた後、タフトブラシでの清掃を追加する事で、磨き残しやすい「歯と歯の間」や「歯と歯肉の境目」のプラーク(歯垢)を効率よく除去することができます。
タフトブラシの使用部位
①奥歯の歯
②前歯の裏
③歯並びが悪いところ
④矯正装置のまわり
⑤被せ物のまわり
⑥抜けた歯のまわり
⑦生えかわり期の生えている途中の歯
タフトブラシの使用後のお手入れは、使用後は流水下でよく洗い、風通しの良いところで保管しましょう。
また取り替え時期は、ブラシの毛先が開いてきたら交換しましょう。
タフトブラシの使い方や、何かご不明な事がございましたらお気軽にご相談下さい。
詰め物が取れた!
お食事中などにガリっといって口の中から出してみたら銀歯だった、
あるいは、白いプラスチックのようなものだけどもしかしたら自分の歯かも・・・
となったことはありませんか?
詰め物が取れてしまう原因は以下にあります。
・詰め物の周囲からもう一度むし歯になった
・何か衝撃があって治療した歯がかけしまった
・詰め物をつけていた接着剤が劣化し溶けだし接着力がなくなった
すぐに痛みがない場合もありますが、何か取れてしまったら早めに歯科医院に行きましょう。
詰め物が入っていた歯はすでに一度削ってあるので、その患部が剥き出しで露出している状態ということです。
放置すると虫歯は進行しやすいですし
隙間にお食事が挟まったままで歯茎の炎症も起こします。
きれいに取れてしまっただけの場合は付け直せる場合もありますので
取れてしまった物は歯科医院に持参するようにしてください。
ただし何年か経っている物に関しては、多少なりとも中が汚れてしまっていることも多いです。
新しくお詰め物を作り直す必要があります。
歯の色
こんにちは
本日は歯の色についてお話しします。
髪の色が明るめの人がいれば黒の人もいるように歯や歯茎の色も人によって違います。
歯の色が黄色味がかっていたとしても、全部の歯の色がそうであればあまり心配ないということです。
しかし食べ物の色が沈着して着いた色の変化は要注意です。
それは歯石のつきはじめと考えられます。
例えばコーヒーや緑茶が頻繁に飲む人の歯には茶渋がついて黄色っぽくなったり歯と歯の間に茶色っぽい筋が入ったりします。
歯石はは歯垢が石灰化して固くなり、歯に付着したものです。
放っておくと蓄積して歯周病の原因にもなります。
日頃からの歯ブラシを丁寧にして石灰化するまえに取り除くことが大切です。
とはいえ研磨剤の入った歯磨き粉を使いごしごし磨くと歯の表面を削ってしまうことになるので注意が必要です。
歯の着色や不十分な歯磨きが気になるようでしたら、月に1度くらいは定期的に歯医者に行くことをお勧めします。
定期的な検診は虫歯予防にも大きな意味があり、口内環境を良い状態で保つことができます。
美容院に手入れにいくように歯科医院へも習慣が一般化することが私たちの願いです。
40~60代のお口の中
【個人差が出てくる年代】
40歳~60歳の年代の方たちの口腔内環境は
それぞれの生活習慣や全身疾患の有無、加齢による変化などで個人差が大きく出てきます。
今までなんとなく治療したり途中で通わなくなってしまっていたり、ちょっと痛いけど気にならなくなってきたので放っておいたり
揺れてる歯が何本かあるけど食事はできてるので特に治療はしていない
といった、
なんとなくやり過ごせていたことが徐々に大きな症状となり最終的な決断をしなくてはいけないタイミングがきてしまうことがあります。
根っこの治療をたくさんしてある方や
歯周病に罹患しておりコントロールが上手く行えていない方は注意が必要です。
神経を取ってある歯は基本的には歯自体の痛みは出ないため、中で虫歯が進行していても症状がないことが多く
また、歯周病も急性症状が出なければ基本的には痛みが無く、ご自身で気づけないケースが多いからです。
しばらく歯医者さんに行っていなかったり不安な箇所がある方は是非一度歯科医院で検査をしてみて下さい。
親知らず
親知らずとは 大人になってから生えてくる最後の永久歯です。
第三大臼歯とも呼ばれ、前歯から数えて通常8番目になるので8番とも呼ばれています。
顎の一番奥に生えてくるため出てくる場所がなく横を向いて生えてきたり、
そのまま前の奥歯にぶつかってしまったり、
磨きにくさから歯茎が腫れてしまったりと痛みのために抜かなくてはいけないことも多いです。
親知らずの厄介な点
・痛み
生える前だけでなく、生え終わってからも歯の上に歯茎が残ってしまい噛むときに歯茎を挟んで痛みが出ることがあります。
・歯茎の腫れ
親知らずは少し生えただけで動きが止まってしまうこともあるのできちんと生えきっていないと周辺に汚れが溜まりやすく炎症を起こしやすい状態です。歯茎が腫れている場合は内部で炎症を起こしており抗生剤などの服用が必要になってきます。
・噛み合わせがおかしい
まっすぐ生えてこなかった親知らずの場合は本来噛み合わせる歯の一本前の歯と干渉してしまうことも多いです。
ずれた状態で噛んでいると顎や歯が痛くなってきたり歯がすり減ってきたりします。
上下の親知らずの数が揃っていないときや噛み合わせにズレがある時に起こりやすいです。
・むし歯になりやすい
歯ブラシが届きにくく生えてきていることに気づかないうちに虫歯になってしまっていることが多いです。
また親知らずが斜めに生えている場合、手前の奥歯も虫歯になってしまい、根の治療を必要としてくるケースも多くあります。
・歯並びが悪くなってくる
親知らずが生えるときに後ろから前の歯を押して前の方にしわ寄せがくることがあります。
トラブルの起きやすい親知らずですが
残しておいていい場合もあります。
ご相談は担当医までお声がけください。
虫歯より怖い歯周病
●血管を通り全身へ広がる歯周病菌
普段の歯ブラシがきちんとできてないと、歯周病菌が歯と歯の間から血管に侵入し、様々な悪影響を及ぼすことが分かってきました。
歯周病菌は菌の周囲の歯肉や歯骨をじわじわと壊し、ゆくゆくは抜歯にいたらせることはよくありますが、実はそれだけではありません。
それは血管内へ入り、全身を駆け巡ることです。歯周病菌は、血栓の発生や血管の壁をもろくする原因の一つに挙げられているのです。
●歯周病治療で全身疾患から身を守る
その他歯周病菌が進行している妊婦は早産しやすいことも明らかになっています。
また、糖尿病と肥満者を対象に歯周病との関連を調べた結果、歯周病になっている人が多い、歯の数が少ない、未処置の虫歯が多い、歯の数が少ない、咀嚼機能が少ないことが判明したそうです。
これらのことから、歯周病は、歯の病気、口腔内の病気だけとあなどれません。
血管の病気でもあるのです。
血管は全身のライフライン。
歯周病を治療することは、全身疾患から自分を守ることにもなるのです。
歯内療法セミナー
新宿パークタワー24階会議室にて
鎌倉デンタルクリニック、神奈川歯科大学付属横浜クリニックの三橋晃先生をお招きし
歯内療法セミナーを開催いたしました。
当法人のみではなく他のクリニックの先生方にもご参加いただき3時間ほどの勉強会となりました歯内療法とは歯の根の治療のことです。
患者様の中でも経験したことのある方は多いと思います。
我々一般開業医の日々の診療でも、根の治療をしない日は珍しいくらい日常的に行う治療です。
今回は最新の手技や薬剤のお話を詳しく教えていただき、
また受講された先生方の日々の診療での相談などに丁寧にお答えいただきました。
教えていただいたことはすぐに日々の治療で活かしていきたいと思います。
次回はアドバンスコースをしていただけるとのことですので楽しみです。
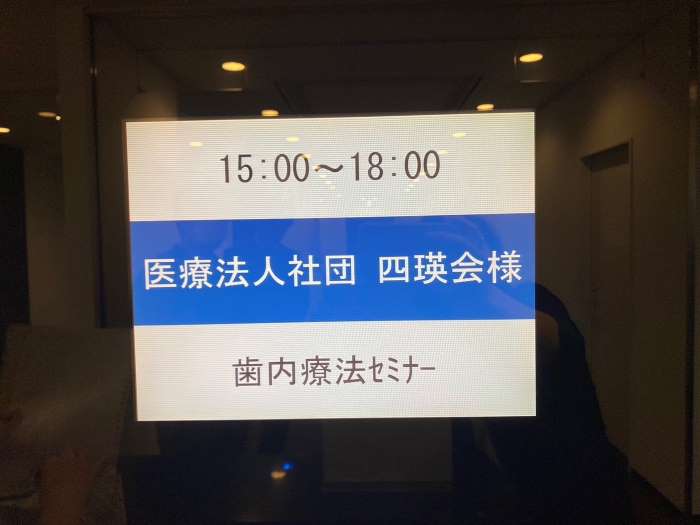

目で見る虫歯の進行
虫歯の原因
虫歯は、プラーク(歯垢)の中にいる虫歯菌(ミュータンス菌)が、糖分を取り込んで
強い酸を作り出しエナメル質を溶かすことから始まります。
しかしエナメル質は水晶ほどの硬さがあるので、表面に付いたプラークを丁寧な歯磨きで
落としていれば虫歯菌から守ることができます。
ここで防ぐことができずエナメル質よりも軟らかい象牙質へ進行すると、次は歯髄へどんどん進行していきます。
歯髄には神経があるのでこの頃になると歯が痛み始めます。
このように虫歯とは、口の中の細菌が出す酸が歯を溶かしてしまう恐ろしい病変のことです。
虫歯の進行
C1 痛みやしみるという自覚症状がまだありません。
そのため、気が付かないうちに進行してしまうこともあります。
C2 虫歯がエナメル質を越えて象牙質に広がります。
この頃までは治療も割と早く済みます。
象牙質には象牙細管という細い繊維があり、冷たいもの・熱いものがしみてきます。
C3 歯髄(神経)が侵されているので、歯髄を取る必要があります。
歯のほとんどが壊されて腐っている状態です。
そのため治療が長くかかり、かぶせ物を被せることになります。
激しい痛みがあります。
C4 歯髄が死んでいる状態です。
歯根膜炎を併発していれば噛んだ時に痛く、根の先に膿の袋が出来ていることもあります。
抜歯せざるを得ないこともあり、治療は困難です。
神経の孔を通って顎の骨に細菌が感染すると顔が大きく腫れることがあります。
痛みがなくても虫歯ができている可能性もありますので、定期的な検診はとても大切です。
検診ご希望の場合はいつでもご相談ください。
仕上げ磨きの重要性
小さな子供さんの場合、歯ブラシの届きにくい場所が多くあります。乳歯の頃から虫歯を予防するために、お母さんの仕上げ磨きは大事です。せめて、1日1回だけでも仕上げ磨きをしてあげるといいですね。
♦具体的な方法
1.仕上げ磨き用の歯ブラシで、上下の表・裏、噛み合わせを丁寧に磨きましょう。
2.歯ブラシの持ち方は、鉛筆を持つようにすると磨きやすいです。
3.お子さんに手鏡を持たせて、歯磨きのやり方を見せてあげましょう。
♦いつまで必要か?
最も虫歯になりやすいのが、6歳臼歯です。
何もないところへ生える奥歯なので、気づいていないことに加え、歯ブラシが届きにくいのが主な原因です。
お子さん一人でも、時々歯をチェックしてあげてください。永久歯が生えそろったことが確認できれば、仕上げの最終ゴールです。
だんだん成長していく子供たちとの大切なスキンシップと考えて、気長に見守ってあげましょう♪
お子さんの口腔ケアでご相談があればお気軽にご相談ください。
唾液の働き
皆様、こんにちは。
今日は唾液の働きについてです。
唾液には、口や体の健康に関わるさまざまな働きがあります。
唾液には主に、耳下腺、舌下腺、顎下腺という3つの大きな唾液腺から1日に1000〜1500ml程、分泌されます。
唾液には、食べ物の消化を助けたり、味を感じやすくしたりする働きや、口の中の汚れを洗い流したり、酸を中和して口の中を中性に保ったり、細菌の繁殖を抑えたり、再石灰化によりむし歯を防ぐといった口の中を清潔で健康に保つ働きがあります。
唾液の分泌量は、ストレスや疲れ、加齢などで減少することもあります。
口の渇きやネバつきを感じることが多い場合には、食事の際にはよく噛むようにしましょう。
唾液の分泌は、夜寝ている間に少なくなります。そのため、夜間に口の中で細菌が繁殖しやすく、朝起きると口の中がネバネバしたり、口臭が気になったりしがちです。
そのため、就寝前にはより丁寧なお口のケアが大切です。
口臭と口臭チェック法
自分の口臭が気になる、口臭がないか心配という方も多いかと思います。
気になりすぎて精神的に落ち込んでしまう方も中にはいらっしゃるほどです。
しかし厳密にいうと口臭がない人はいません。
誰でも食べた物のにおいを含め、何らかのにおいがあるでしょう。
ただそれが、他人に不快感を持たせる程度なのかどうかが問題なのです。
口臭のチェックをしてみましょう
- コップに息を吹き込んで手で塞ぎ、一拍置いてからにおいをかぐ
- 舌に白い苔のような物があれば、ティッシュなどでふき取りにおいをかぐ
- 家族に息をかいでもらう
口腔内のチェックをしましょう
- 大きな虫歯がある
- 歯磨きをすると歯肉から出血する
- 歯肉を押すと膿のようなものが出る
- 歯と歯の間に食べ物が詰まる
- 歯が浮いた感じがしてグラグラしている
- 唾液が少ない気がする
- タバコを吸う
- 義歯やブリッジを使っている
- 就寝時に歯磨きをしないことが多い
口臭チェックで大丈夫であった人も、口腔内のチェックで3つ以上当てはまる項目があれば
遅かれ早かれ口臭がするようになる可能性があります。
治療しなければいけない虫歯や歯周病があれば、しっかり治しましょう。
口臭を気にするあまり、人生の様々なシーンで大切なチャンスを逃してしまうのは
とても残念なことです。
反対に口臭が不安な方でも、両方のチェックで何も当てはまらなければ気にする必要はありません
のでご安心ください。
ご心配なこと、気になる事などあればご気軽にいつでもご相談ください。
生え変わらない乳歯
生まれつき永久歯が少ないことは珍しいことではありません。
乳歯が生え変わらず小学校の検診でチェックがあったり
大人になってから歯科医院で指摘されるケースも多いです。
本来ならば生え変わり時期に下から生えてくるはずの永久歯に押されて乳歯が抜けるはずですが、
永久歯が存在しないといつまでも乳歯が残ります。
顎の形などの骨格や歯並び、歯の大きさや質などは遺伝も要素も大きいです。
しかし親知らずのように人間の進化の過程で退化してしまうものもありますので
一概に遺伝とひとくくりはできませんが、気になる方はレントゲンを撮るなどして確認してもいいかもしれません。
後続の永久歯がなく残された乳歯は、長く使えるケースと、途中で抜けてしまうケースがあります。
その後を補う方法は
・入れ歯
・ブリッジ
・インプラント
・矯正
等がありますが、その時の年齢や前後の歯の健康状態、予算などによっても異なってきます。
どちらにしても抜けたままはよくないですので歯科医師と相談して治療方針をきめていただくとよいでしょう。
矯正治療
子どもの頃矯正治療をしていたけど大人になって少し後戻りが気になってきた方や
そこまで大きなガタつきは無く今まで矯正治療はしてこなかったけれど、
前歯のズレがやっぱりちょっと気になる・・・
といった方も多いと思います。
矯正治療には
全体矯正と部分矯正があります。
症例によっては部分矯正で済むケースも少なくありません。
また部分矯正の中でも、
治療方法としてワイヤー矯正とマウスピース矯正があります。
ワイヤー矯正はご自身で取り外しができませんが24時間力がかかりますのでマウスピース矯正より動きが速いことが多いです。
ただ、取り外しができない分、歯磨きがきちんとできないと虫歯や歯肉炎のリスクはあがってしまいますし、
見た目も装置がついていることは分かってしまいます。
マウスピース矯正はご自身で取り外しができる為、お食事の時や歯磨きの時は外せますし、
お写真を撮ったり何かイベントの時には外しておくことができます。
ただ、取り外しができる為ご自身で装着時間の管理をしていただかないとなかなか動きが悪いことがあります。
ご自身のライフスタイルや性格なども考慮して決めていただくといいと思います。
またワイヤーとマウスピースでは得意とする動きも異なる為、
歯並びの状態によっておすすめの治療法があると思います。
主治医と相談してみてください。
虫歯予防のフッ素
みなさま、こんにちは。
今日は、フッ素についてです。
フッ素がなぜ虫歯予防に有効なのはご存知でしょうか。
①歯の質を強くします
②初期虫歯で溶かされた歯を再石灰化する作用があります
③口の中にいる雑菌の働きを弱くします
いかがだったでしょうか。
フッ素は、歯磨き粉以外にも洗口水などで手軽に取り入れることが可能です。
できるだけ毎日、歯磨き後に、フッ素入りの洗口水でぶくぶくうがいをするようにしましょう。
インプラント周囲炎について
インプラント周囲炎という言葉をご存知ですか?
インプラントに起きる歯周病を「インプラント周囲炎」と言います。
インプラントは人工の歯だから虫歯や歯周病にはならないと考えている人もいますが、それは違います。
インプラントは人工の歯なので虫歯になることはありませんが、メンテナンスを怠ると歯周病になるリスクはあります。
インプラント周囲炎になってしまうと、歯茎に炎症が起き、顎の骨が溶かされ、インプラントがグラグラしてきます。
そのままにしていると、せっかく外科手術までして埋め込んだインプラントが抜け落ちてしまう可能性のある恐ろしい病気です。
インプラントをトラブルなく長きにわたって使い続けるには、適切なメンテナンスが欠かせません。
ご自宅でのブラッシングを怠ったり、定期検診に行かなかったりすると、口腔内環境が悪化してインプラント周囲炎になるリスクは高くなります。
そうならないためにも予防が大切です。
インプラント周囲炎を予防するには、喫煙者は禁煙をすること、毎日のブラッシング等のセルフケア、そして定期的なメンテナンスが必要です。
当院では他院で入れたインプラントのケアもさせていただきますので、いつでもお気軽にご相談ください。
プラークについて
皆様、こんにちは。
今日はプラーク(歯垢)についてです。
プラークとは、歯の表面に付着している細菌のかたまりです。
白色または黄白色をしているので、目では確認しにくいのですが、舌で触るとザラザラした感触があります。
プラークはネバネバと粘着性が強いため、歯の表面にしっかりと付着し、強くうがいをしても取れません。
プラーク中には、細菌が約600種類も存在しているのです。
①プラークの付着の原因
プラークは口の中の清掃が、十分になされていない歯の表面に形成されます。
②プラークの形成
歯の表面に、唾液の中の糖タンパク成分が膜のように付着します。(ペリクル)
ペリクルに細菌が付着し、定着、増殖することでプラークが形成され、どんどん成長していきます。
③プラーク付着の予防方法
プラークは、むし歯や歯周病などの口の中の様々なトラブルの原因になるため、毎日セルフケアを実行し、歯科医院で定期的なクリーニングを受けて、しっかり除去することが大切です。
1 セルフケア
・丁寧な歯みがきを心がけましょう
・歯と歯の間もしっかりケアしましょう
2 プロケア
歯石や歯周ポケットの中などのセルフケアでは除去できない汚れは、歯科医院でクリーニングを受け、除去しましょう。
気になる事など、何かございましたらお気軽にご相談下さい。
歯の形と役割
こんにちは。
本日は歯の形と役割についてお話しします。
大人の歯は32本で、8種類あります。
ただし1番奥の歯、親知らずと呼ばれている歯がなければ28本です。
歯はいろいろな形があります。
ひとつずつ確認してみましょう。
1番目の歯は中切歯(門歯、切歯) 食べ物をかみ切ったりちぎったりするので中切歯ともいう。
2番目の歯は側切歯 前歯の仲間。
3番目の歯は犬歯(糸切り歯) 八重歯は顎が小さすぎて歯列の外側にはみ出してしまった犬歯のこと。犬歯は歯の中で最も平均寿命が長く、噛み合わせ等に重要な歯。
4番目の歯は第一小臼歯 ここから奥歯。小さい臼歯で臼という感じの通り、食事をすりつぶす役割を持つ。
5番目の歯は第二臼歯 これも小臼歯。
6番目の歯は第一大臼歯 ここから大臼歯。6歳のころに生えてくるため6歳臼歯ともいわれる。噛んだり噛み合わせたりするのに大切。
7番目の歯は第二大臼歯 大きくて頼りがいがある。十二歳臼歯ともいわれる。
8番目の歯は第三大臼歯 親知らずと呼ばれる。大人になってから生えてきたり、生えてこない人もいる。
それぞれの歯が食べ物を小さく切ったり、砕いたりするなどの大切な役割を持っているのです。
歯1本1本大切にしましょう。
大変?歯のぐらぐら動揺
指で歯を挟んで動かしてみると、少し動くと感じた人はいませんか?
歯周病が進行すると歯がぐらぐらしてそのうちに抜けてしまいます。
しかし健康な状態でもある程度のぐらぐら動きはあるのです。
そもそも歯は歯根膜というクッションのような組織に包まれていて、歯槽骨と直接くっついてるわけではありません。
指で動かすと、このクッションの働きでわずかに揺れるようになっているのです。
では注意すべき動揺どんなものかを説明しましょう。
・指で動かさなくても上下の歯を嚙み締めただけで揺れを感じる場合。
・指で前後左右に動きを感じるのではなく、上下に動く感じがする場合。
こういった動揺がある時は、歯周病がかなり進行してると考えられます。
歯はいきなり全部の歯が動き出すことはなく、まず特定の歯が動き出すことが多く
なかでも虫歯でも治療済みでもない歯が動き出したら注意が必要です。
もし思い当たる症状があったらお早めの受診をお勧めします。
奥歯にかかる力
食事をする時、歯や歯茎には意外と大きな力がかかっています。
前歯には約20キロ、小臼歯には約30キロ、大臼歯には約50キロの力がかかっています。
食事だけではなく、様々なシーンで奥歯は私たちの生活に大きく関わってきています。
例えば椅子から立ち上がる時や重い荷物を持ち上げる時など無意識のうちに奥歯を噛み締めていることがあります。
またゴルフやテニス、バッティングなどのスポーツをする時も衝撃を受ける際に奥歯をかみしめるケースが多いです。
スポーツによってはマウスピースの装着を義務付けているものもあります。
つまり力を入れる時の踏ん張りを支えているのが奥歯です。
健康な歯肉と健康な歯牙を持っていれば奥歯というのは大きな力をしっかりと受け止めかたい食べ物もかみ砕く非常に重要な存在ですが、
虫歯や歯周病が進んでしまっていると存分な噛み締めをすることができません。
奥歯は歯ブラシが届きにくい上に前歯より複雑な形態をしており、また上記のとおり力もかかるので虫歯やトラブルが起こりやすいですができるだけ大切にして長持ちさせたいものです。
奥歯を失い、そのままにしておくことは食事がしづらいだけでなく全身のバランスを崩すことに繋がりかねません。
歯ブラシの使い方
歯ブラシを使った磨き方は色々な方法があります。
●縦磨き
歯ブラシのつま先を使った磨き方です。
毛先が届きにくい奥歯の咬合面や奥歯の後ろ側を磨く時におすすめです。
●横磨き(バス法)
歯と歯茎の境目に、歯ブラシのエッジを当てるような感じで当てます。
軽く歯を1本ずつ磨くことをイメージしながら横に5ミリくらいの幅で軽く動かします。
●水平磨き
奥歯の噛み合わせ部分は、歯ブラシを横にして、できるだけ細かい動きにして、歯の表面の溝のたまった汚れを取り除くイメージで磨きます。
いかがだったでしょうか。
歯磨きの方法も様々あるので、自分の歯に合わせた方法試して実践してみてください。